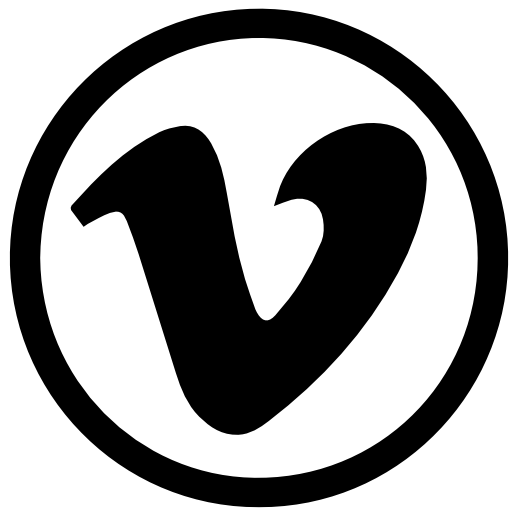見たい!知りたい!演劇業界!悩まず進め!!
~劇団かかし座~
週刊メールマガジン 演劇タイムズ
VOL.174 [2005/7/25] 掲載
日本で活動している劇団は数限りなくあります。しかし、そのほとんどが一般に知られていないのが現状です。日本の演劇業界が、他のエンタテイメント業界、アート業界に比べ、マイナーであり続けているのには、必ず、明確な問題があるはず―――。
このコラムでは、現在活躍している劇団に取材し、劇団の現状やそれぞれが抱えている問題点、演劇全体が広く社会に認識されるにはどうしたらいいのかなどのテーマを共に考え、演劇の魅力をより多くの方々へ知っていただくための方法を考察してゆきます。
第33回目の今回は、劇団「かかし座」です。
●劇団かかし座
1952年、後藤泰隆(とうたいりう)によって創立された、日本初の影絵専門の劇団。当初、NHKの専属劇団としてテレビ影絵劇の上演をスタート。その後、技術の発達にともない全国巡回公演を開始。
影絵の世界が持つ「人々の心を無限の想像へ駆り立てる、ふしぎな性質と魅力」をもって、たくさんの人々の心に夢を育てたいという思いで、TV、映画、舞台、出版などを通じて提供し続けている。
また、近年では新しい技術を取り入れながら、影絵劇の新たな可能性を模索している。
●劇団代表・後藤圭さんにお話を伺いました
日本には、影絵を専門とするプロの劇団が非常に少ないのをご存知ですか?実は、7~8団体しかないそうです。でも、皆さんの心のどこかに、昔見た懐かしい影絵の不思議な世界が広がっているはず。
子どものころに見たNHKの影絵劇や、昔教えてもらった手影絵。振り返ってみると、いろいろな思い出が出てくるのではないでしょうか。そのほとんどが、かかし座さんのお仕事だったようです。
今回は、日本を代表する影絵専門の劇団「かかし座」の代表・後藤圭(ごとう・けい)さんに、影絵の世界の裏側と、今後の方向性についてお伺いしました。
Q・影絵というのは、いつごろからあったんですか?
―――― なかなか文献が残っていないんですが、そうとう昔からあったようです。中近東なんかでは、風刺や笑いを中心に演じていたようですし、中国大陸でも盛んでした。日本でも江戸時代にはすでに影絵劇一座がいて各地を廻っていたようですし、影絵売りという商売があったようです。
「からくり燈籠」と言って、ランプの熱を動力にして紙の人形が廻る燈籠も古くから作られていました。絵を動かして遊ぶということは昔からあったんでしょうね。元祖アニメといったところでしょうか。江戸時代の後期には、日本独自の仕掛けをして、かなり精密に動くようになっていたようです。
ただ、明治から戦後にかけて文化の分断があったんです。古い伝統は駄目で新しいものを追い求めようという風潮になって、その中で徐々に姿を消していったようです。
かかし座を創立したのは父なんですが、戦後に海外から入ってきたシルエットなどを参考にして始めたという話を聞いたことがあります。だから、昔のものをやっているという気はなくて、むしろ新しいものを求めて始めたようですね。
Q・影絵と科学技術には大きな結びつきがあると聞いたのですが、どういう関係
があるんですか?
―――― 昔は影を映し出すために、スクリーンの後ろでランプやロウソクを使って火を焚いていました。
影っていうのは、光源が小さければ小さいほど、そして、色温度(※)が高ければ高いほどシャープな影ができるんですよ。炎の光っていうのは温かみがあっていいんだけど、影を出すには光源も大きいし色温度も低いんです。それが、技術の発達と共にライトができて、炎よりも安全な光源を手に入れることができました。
そうはいっても、最初はとっても大きな電球を使っていたし、光も今よりは弱かったんです。だから、舞台で影を出そうとすると、ベニヤを切り抜いて大きな人形を作らないと駄目だったんです。地方を巡回するとなると、とってもたくさんの機材を運んで行かなければいけないので、本当に大変だったようです。
それが、OHP(オーバー・ヘッド・プロジェクター)という機材ができ、今はハロゲン球やクセノン球、LEDなどの開発でさらに小さな光源で色温度の高い明かりを手に入れることができました。
また、コンピューターの導入によって、光の具合や影の効果も広がりを見せています。デジタルな環境が、こういったアナログな世界を引き立ててくれているわけです。
Q・かかし座では、影絵を見せるだけでなく、役者がスクリーンの前に出てお芝居もしていますが、この方法は珍しいですよね。こういった表現方法を始めたきっかけは何ですか?
―――― 芸能には「保存」と「開拓」の2つの方向性があると思うんです。私たちは「開拓」を選んだというか、生の演劇としての影絵劇を模索して、試行錯誤してきたんです。
スクリーンがあって、後ろでは人形を操作する人がいて、前には語り手がいるというのが影絵劇の原風景です。ただ、そうすると影絵劇団なのに影絵をやらない人がいて、お芝居なのにお芝居をしない人がいる。これっておかしいんじゃないかって思ったんです。それで、分業はやめて、全員が人形の操作もするし芝居もするというスタイルを作りました。
それと、影絵劇のほとんどが、スクリーンを立てたら袖を隠すんです。芝居や音楽はパッケージにして、テープをスタートさせたら後は絵をあててゆくだけというスタイルなんです。でも、それはあまりにもお芝居とかけはなれているんじゃないか、ていう疑問が出てきたんです。
だから、私たちは録音を使わず、袖を隠さず、後ろで人形操作をしている人も前に出て芝居をする人も同じ空間にいて、お客さんも一緒にいるという環境を生み出しました。それが演劇として一番正しいという思いがありましたね。
人によっては、「かかし座は影絵を捨てた」なんて言われますが、そうじゃない。あくまでも影絵劇だし、それをより伝えるための手法として役者がスクリーンの前に飛び出していくというスタイルを生み出したということです。
Q・影絵劇を取り巻く環境の中で、何か問題点はありますか?
―――― 正直、問題点ばかりですよ(笑)
まず、全体的に保存の方向に傾いているということ。人形劇、影絵劇の歴史は戦後60年あるわけですが、60年間同じ形であることはありえないんですよ。「自分たちは保存するんだ」という覚悟であればいいですけど、結局芸能は現在形で生きてゆかなきゃいけないですから、変わっていった方がやる側にも観る側にもプラスになるんじゃないかと思いますね。
それと、マーケットが狭いです。世界的に見ても、児童演劇のステータスは低いですから。大人社会なので仕方ないことなのかもしれませんが、子どもを大事にしようということで、子ども向けのお芝居のステータスが上がるのは大切なことでしょうね。
でも、今の日本ではこれ以上の助成がでるとか、学校教育の中で鑑賞機会が増えるというのはありえないと思います。
だから、自分たちで経済的な基盤を整えることが大切でしょうね。事業として成り立たなければ消えるしかないわけですよ。昔は作り物の絵が動くだけで面白いと思ってもらえましたが、今ではたくさんあるコンテンツの中の1つな訳です。
現代で事業として成り立つ方向性を探し、現代との折り合いを付けてゆかないと駄目でしょうね。その中で芸のあり方が変わってゆくのは当然のことだと思います。
素朴な感覚を必要とする人の心に、どれだけ訴えかけてゆけるか。そして、それがいかに売れるものであるか。そこのせめぎ合いなのかもしれませんね。
後藤さんは、とても明るくフレンドリーな印象をうけました。舞台芸術を取り巻く環境を話す時、私を含めほとんどの方が眉間にしわを寄せて語るのに対し、後藤さんは笑顔でこうおっしゃいました。
「問題は山積み。でも、悩んでいても仕方ない。新しいものをドンドンと取り入れて、前に進むことが一番大切ですよ」
このフットワークの軽さが、50年以上も影絵劇団のトップとして存続し続ける秘訣なのかもしれませんね。
(構成・文/O)
※色温度:色温度とは、光源の光の色合いを、物理的、客観的な尺度で表したもの。一般的に温度が低ければ赤く見え、温度が高くなるにつれ青く見える。